その結果、2つのボット(メインとメーリングリスト)が作成され、その上で管理が落ち着き、samizdatを開始しました。
もう一度プロトタイプを試してみたところ、テレグラムスタックに他の興味深いものをすばやく書くことができるようになりたかったのです。 選択肢はコメントにかかっていました。
電報チャネルのコメント用のボット@CommentsUserBot
電報にはチャンネルがありますが、コメントすることはできません。また、ニュースを書くことができないチャットもあります。 ミュートにすると、すべてのスパムメッセージを受信するか、何も受信しません。
ただし、チャットで通知を使用してピンを実行すると、#channelで別名の公開をエミュレートできます。
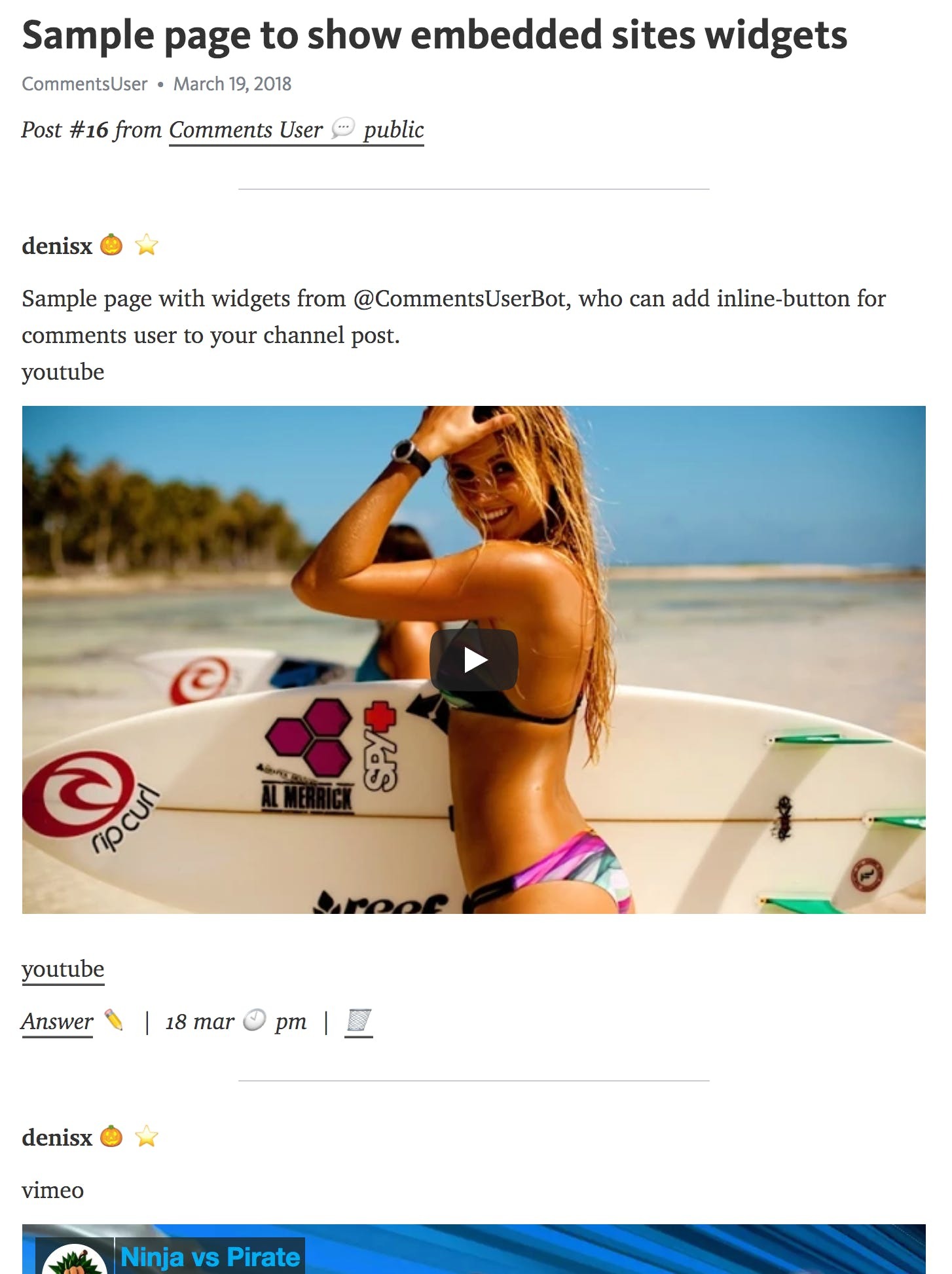
熟考したら 、 telegra.phのドキュメントを読みに行きました。 私はすでにIVの企業サイトのニュースパーサーを作成する必要があり、プラットフォーム上にどのウィジェットが存在するのかをある程度知っていました( ただし、一部は開始しませんでした )。 また、ボット開発者のコミュニティでは、後で役立ついくつかの非公開APIを入手しました。
すべてが明確に見えたので、週末に電報チャネル用のコメントボットのプロトタイプを作成しました。ボタンを投稿に固定し、テキストを書き込むボットへの移行、そして電信でのコメントページの生成を行いました。 チャンネル自体では、ボタンにコメントの数が表示されます。
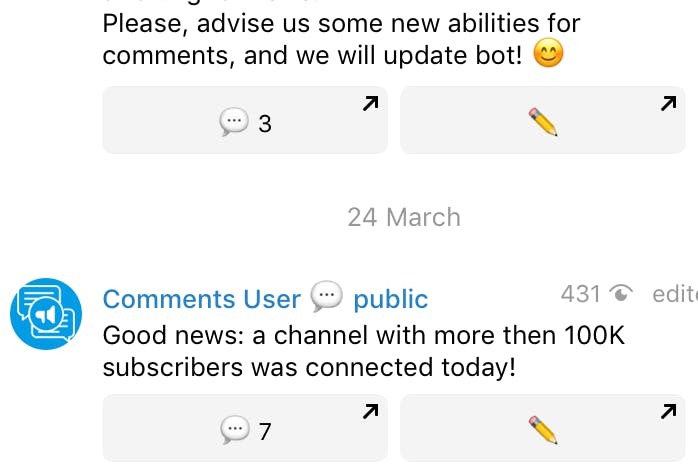
技術的には、サーバーはコメントが投稿されたときにのみ機能します。 それ以外のすべて-テキストとグラフィックス-は、電信自体によって保存およびキャッシュされます。
開発者をテスト用に詰め込んだ後、フィードバックを収集し、計画をスケッチし、静かに変更を提出し始めました。 そのため、最初はチャネルの自動更新モードが設定に置き換えられました(手動または自動、元の投稿の置き換えまたはコメント投稿の投稿)。 コメント自体には、ウィジェット、グラフィック、ビデオが追加されました(脆弱性をテストしてくれたOleg O.に感謝します。ところで、彼は優れたコメントボット@CommentsBotも持っています )。
そのとき、私はtelegram-xをインストールしました。その重要な更新の1つは、ボットに登録すると、ディープリンクから入力するたびにスタートを押す必要がなかったことです。コメント、フラットチャットは既に存在するため、ツリーのようにすることが決定されました。 以前はそのようなストレージを作成しませんでしたが、いくつかのグーグル記事の後、データベースはそれらを消化することができました。 分岐の深さの現在の制限は10レベルです。 20ページのコメントの数、ブランチの回答の事前表示、コメントの数、およびページネーション。
はい、電信はページのデザインを変更することはできませんが、それはまさに必要でした- 電報エコシステムのボット-サイトへの追加の承認とアクセスはありません。 フォントが飛び散ることはなく、コメントページ自体はインスタントビューで機能します 。 その後、ユーザー自身が、通常の形式で、電文、絵文字、ステッカー、リンクなどを含むコメントを詰め込みます。
編集は、現在のコメントの追加に置き換えられます。 一般に、これで十分です。自分のコメントを(コメントページから直接)削除できるからです。

次に、ボットが大きなチャネル( > 10万人のサブスクライバー )を使用したいときに、管理の問題が発生しました。 不快なコメントとユーザーの禁止の削除が追加されました。 また、スパムに対する個人的な敵意により、ユーザーへの返信の通知はデフォルトでオフになっていますが、この設定により、すべてのコメント、コメントのチャンネル/投稿、コメントレベルの選択を購読できます。 これらはすべて別のボットスパマーから取得されるため、電報インターフェイスの知らない人によってブロックすることにより、他のチャネルにコメントを書き込むことができます。
gimpで設計されたアイコンは、すべてのプロジェクトエンティティ(ボット、通知ボット、プロジェクトニュース、サポートチャット)にペイントされます。
言語インターフェースについて: enの電信ページ、 en / ruのボット(自動検出機能)。
コメントは南アメリカで大いに行きました。 現在、優れたサマリア人は、より多くのローカライズのためにgithubでファイルを翻訳しています。春に(夏に?)、ILVがアクセスをブロックし始めたとき、私が開発するのは少し不便になりました(電車で、/ c仕事への道-サーバーへのダブルsshは定期的に落ちます)。 今、私はレビューを収集し、改善計画を作成し、時々別のボットを作成します。これらの開発は現在のプロジェクトで必要になります。
電報チャネルのコメント用のボット@CommentsUserBot。
接続、作成、議論)